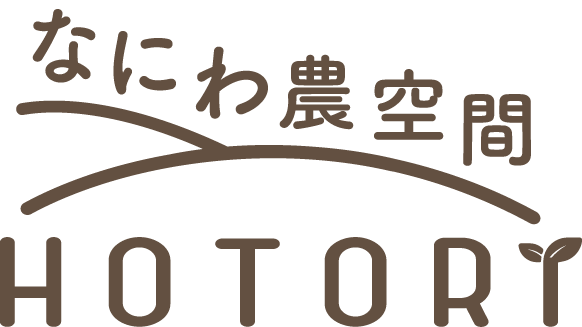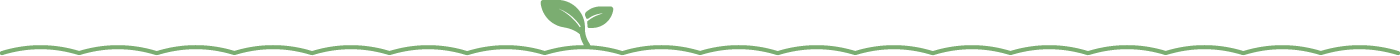2025年5月25日
持続可能な農空間づくりをめざす交流会
2024年3月17日(日)に大阪・梅田の大阪市立総合生涯学習センターにて、「なにわ農空間HOTORI交流会」を開催。「なにわ農空間HOTORI」プラットフォーム会員をはじめ、農業に興味のある団体や企業、個人など18人が参加。企業同士のマッチングや農空間を活性化していくための課題や新たな取り組みについて意見交換が行われました。

まずは、大阪府環境農林水産部農政室整備課参事 田中好輝氏が挨拶。日本の農業は、少子高齢化・後継者不足などにより、厳しい状況にある反面、最近では、環境や教育の面で取り上げられる機会が増えてきたといいます。交流会によって生まれる新たな取り組みやアイデアに期待を寄せると同時に、「農業の価値や可能性を大阪府民に知ってもらえるように、農業に従事する人たちと農業に興味をもっている企業・個人と一緒に活動していきたい」とアピール。

今年度実施した2件の農業体験モニターツアーで浮上した告知方法や価格設定、交通の便やトイレ問題など、さまざまな改善点が報告され、協力団体であるNPO法人里山ひだまりファーム、くまとりこもれび菜園による各ツアーの感想報告も。
小学校・幼稚園で米作りや芋堀りなどの体験学習を行っているNPO法人里山ひだまりファームの内見宏昭さんは、1月に行われた「麦踏みと里山のおもてなし」について、「麦踏みとパン焼きを同時に体験できたので、参加者に大変喜んでもらえました」と嬉しい報告が。一方、交通の便やトイレの場所、設営のためのコストなど屋外開催のイベントならではの問題があり、「パン焼き体験は、アルコール消毒など衛生面にも注意が必要」と今後の課題についても発表。

熊取町を中心に、YouTubeを通して農業に関する情報を発信し、半農半Xを実践しているくまとりこもれび菜園の岩崎則重さんは、2月に行われた「ふわっと就農体験」を監修。講演と収穫体験をセットにしたツアーは、新規就農への関心が高まったという参加者の声が。今後は、家庭菜園のためのセミナーをプラスした収穫体験などを計画中だという岩崎さん。「秋の収穫時期に向けて、体験農園や収穫体験を積極的に開催していきたいです」と力を込めて語ってくれました。

続いては、18人の参加者が簡単な自己紹介と活動内容の報告を行ったあと、少人数のグループに分かれて、「若い人と農業を一緒に行うには?」というテーマで約20分のディスカッション。それぞれが普段の活動の中で実践していることや応用できそうな事例を共有することに。

スリーエスの喜多悌子さんは、「若い世代と高齢世代が話し合うためには、互いにリスペクトすることが必要。若い世代が話しやすいように気をつけてあげなければならない」と指摘。親子向けのお菓子教室を運営している近藤織恵さんは、「子どもを持つ親世代も若い世代に含まれるので、子どもの記憶に残る農業体験を積極的に取り入れることで、農業に興味を持ってくれる人が増えるのでは」と提案。

大阪大学もったいないーとの勝山楓矢さんが指摘したのは、「若い人はもちろん、各年代がまんべんなくいなければ、意志の疎通が難しい」という点です。さらに若い世代が農業をはじめにくい理由について、「農地や働き手の確保や独学の難しさがある」と、若者世代の視点から、意見を述べていました。

株式会社マナビーズの野谷昌平さんも同じく、「やりがいを見いだせない」「報酬が不安定」「農地取得のハードルの高さ」が、若い世代に農業に従事する人が少ない理由だといいます。「ほかの職業なら、例えばスポーツ選手などには憧れの存在がいるが、農業に憧れを抱く人は少ない。農業の魅力がもっと伝われば、若者も興味をもってくれるのでは」という意見も。

多種多様な業界で活躍する企業や個人が意見交換することで、新たな気づきを得ることができたディスカッション。最後には、自由に名刺交換やマッチングができる時間も設けられ、参加者は新たな人脈を構築。農空間の活性化やビジネスの発展につながる有意義な時間を過ごすことができました。